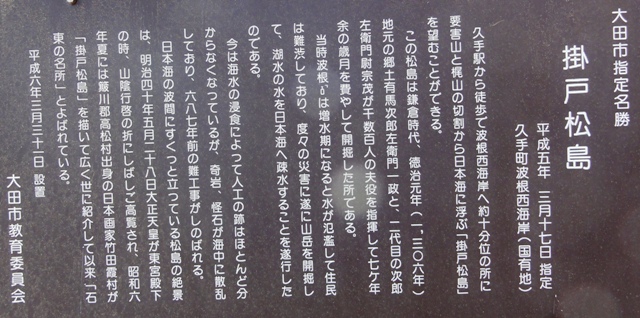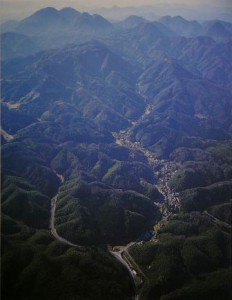空にそびえる草原
洲 浜 昌 三
広大な草原の海原が 目の中に飛び込んできたとき
山育ちのぼくの世界は砕け散った
ー草原(くさはら)が空までつづいているー
昭和三十年高校生の時のこと
その後この山は国立公園に指定された
「全山が芝 根笹でおおわれわれ
世界的にも貴重な草原風景の美しさ」
それが指定の根拠になったという
昭和三十八年のこと
この美しい山を再び訪れた
国立公園指定審議委員の沼田氏は
「昔の面影はまったくない 指定を外すべきだ」
と語ったという
平成三年のこと
30年の間に何があったのか
牛の姿が広い草原から消え
雑草や雑木が自由に伸び伸びと育ち
山頂近くまで杉やカラ松が植えられ
貧しかったこの国は
世界第二位の経済大国になった
牛の放牧は江戸の初期に始まるという
明治元年 3000頭
昭和33年 1766頭
昭和41年 743頭
標高1126メートル 山頂までつづいた
美しい風景は
牛と大地が生み育てた草原だったのだ
350年の歳月をかけて
写真は北ノ原です。後ろの親三瓶は木が密集していますが、昔の三瓶の写真をみれば一面きれいな草原です。
島根県詩人連合では、続「しまねの風物詩」刊行を計画しています。平成25年5月26日の総会へ提案します。島根の風物や歴史などを詩にし一般の人たちに読んでもらおうという企画です。誰でも応募できますが編集委員会で審査します。