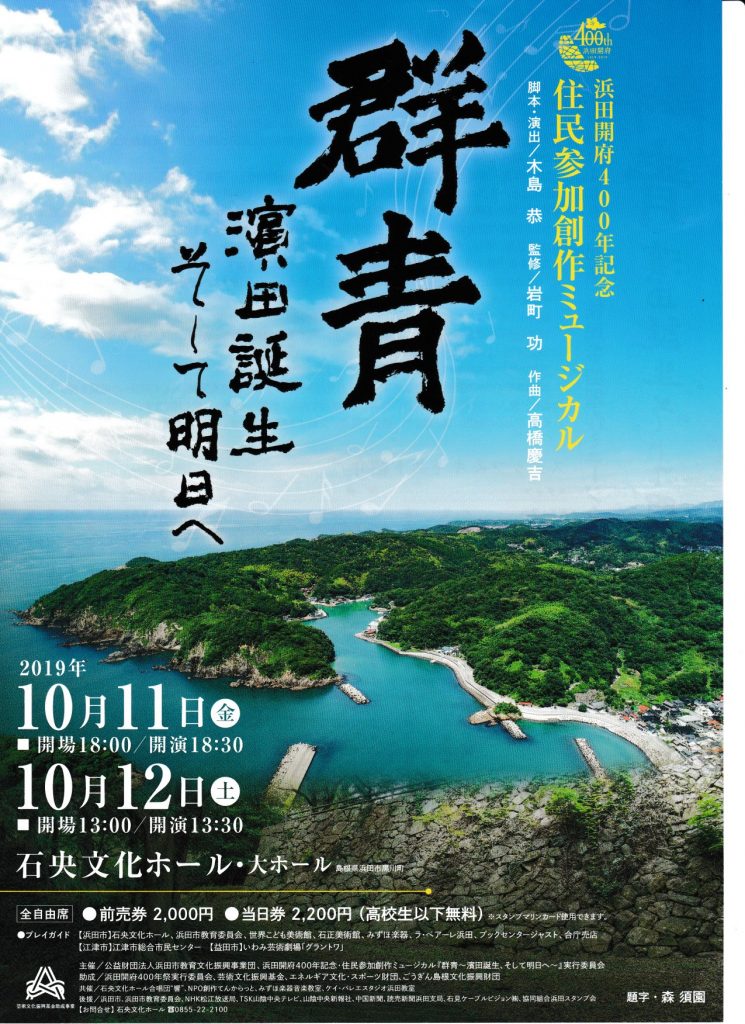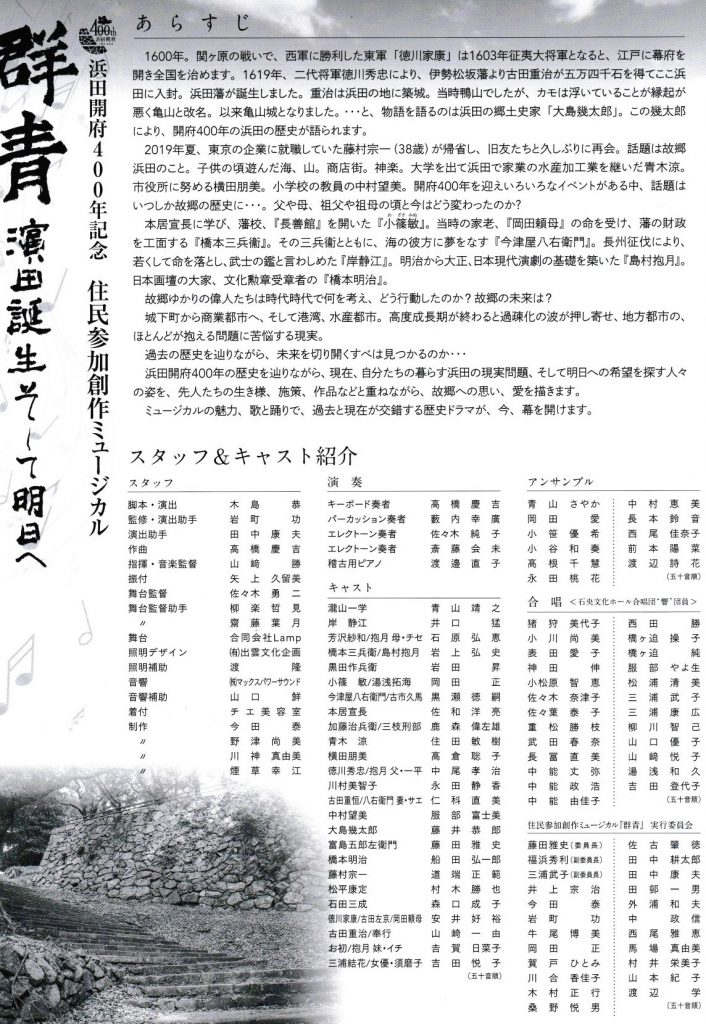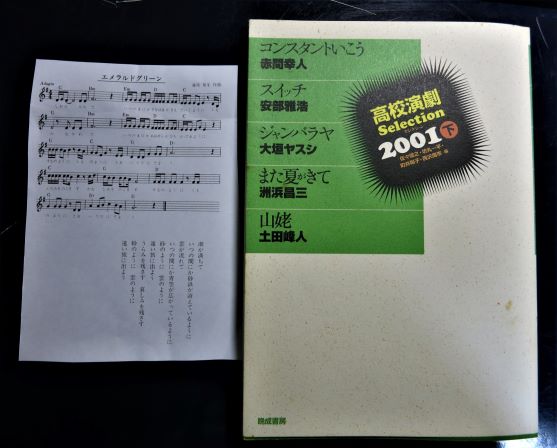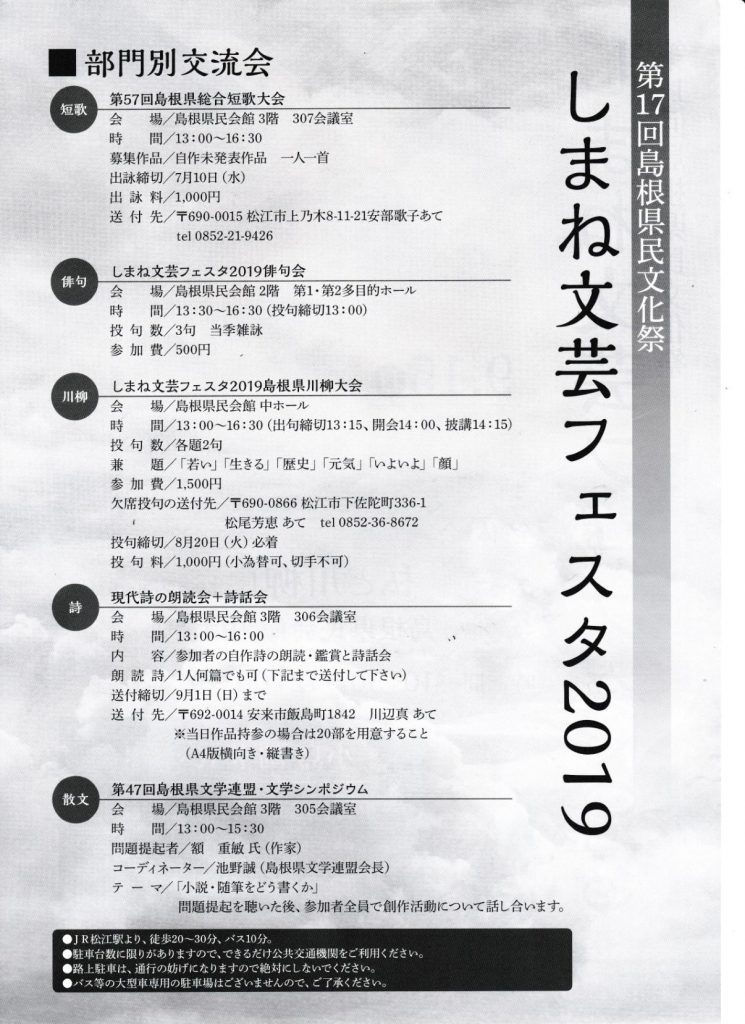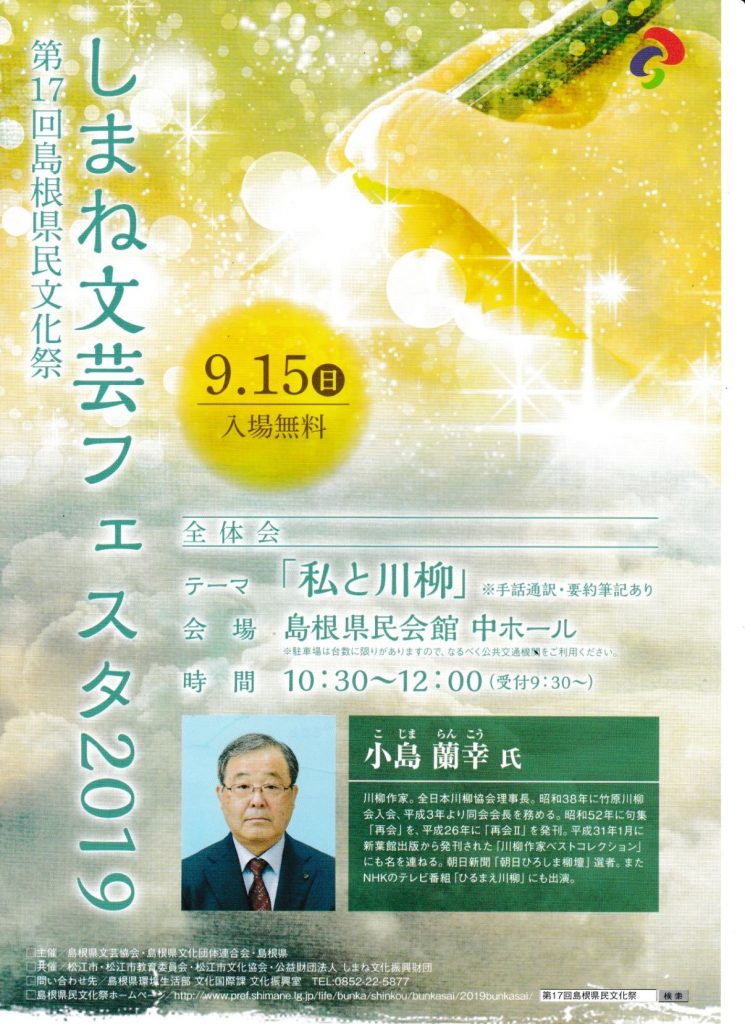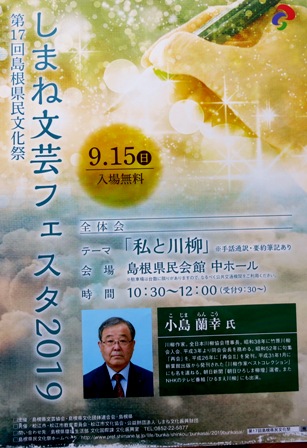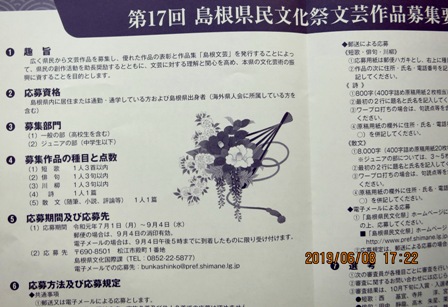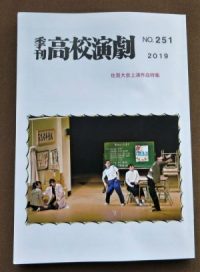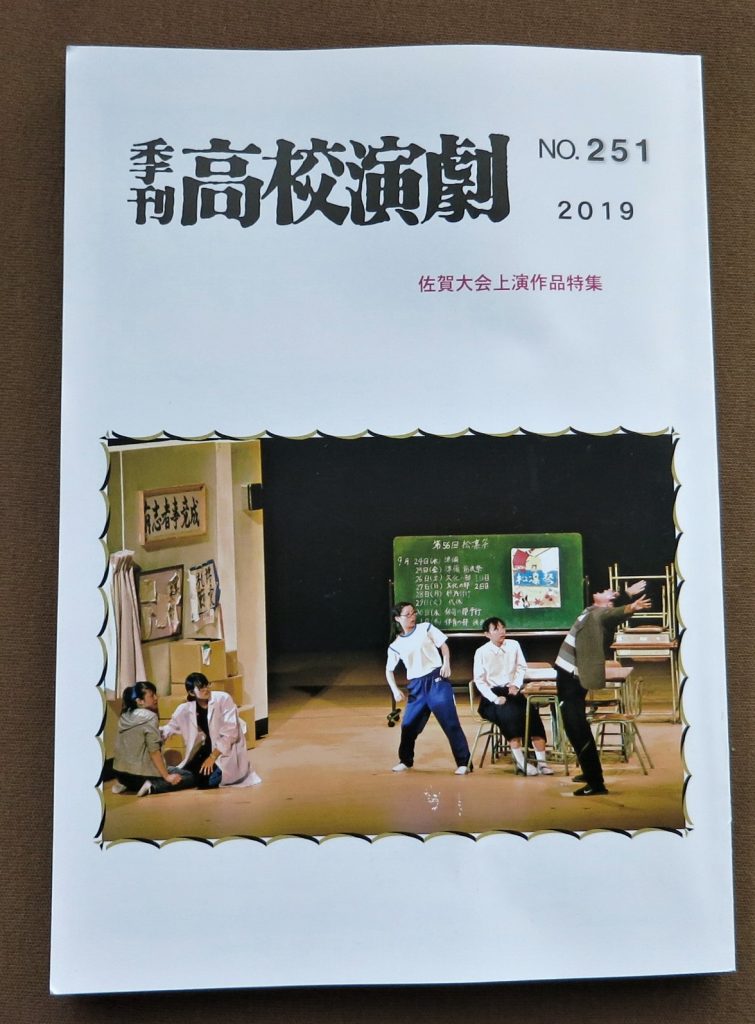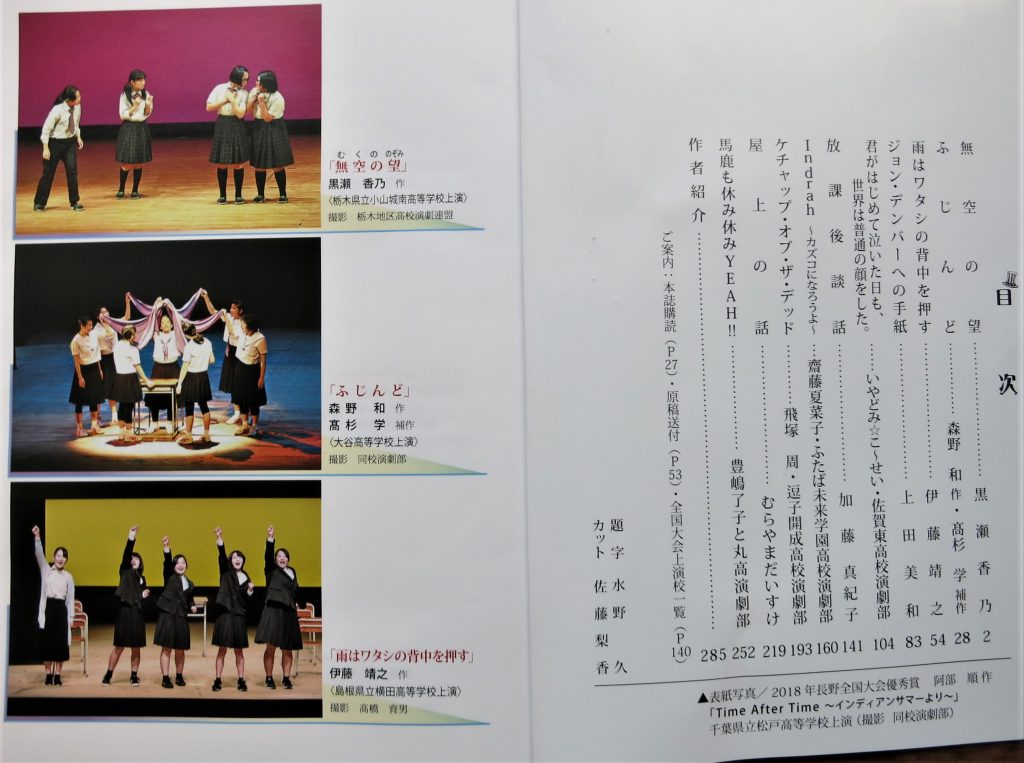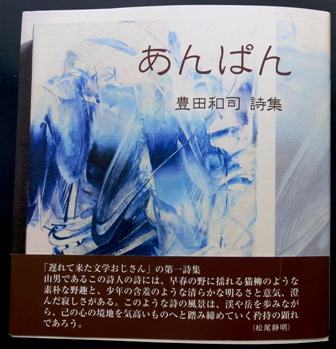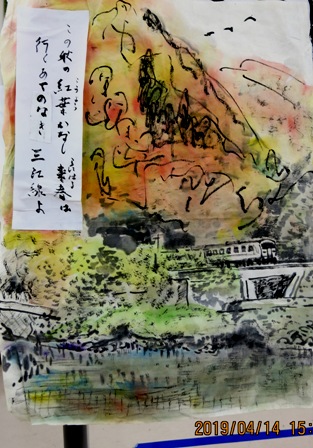10月27,28日、大田市民会館で最後の練習が行われました。30日には東京文化会館でリハ―サル、31日18:30~よいよ本番です。子供たちも伸び伸びと楽しそうに何度も熱心に練習していました。プロの演出・吉田知明さんや、音楽の中村匡宏さんがおられなくても、きちんと細かく連絡を取り合って指導される実力のある指導者が大田におられるということが最大の強みです。この人たちがおられなかったら、レベルの積み上げができません。

役を演じるレジェンドの5人もおられないし、ソプラノの坂井田真美子さんもメゾソプラノの松浦麗さんもおられない練習ですから、普通だったら不自然な動きや流れになって当然ですが、全く不自然さがありませんでした。それどころか無言の動きや流れの中に物語が生まれ、見ていてとても楽しく、感動しました。ぼくはちょっとセリフや動きのアドバイスをしただけですが、すぐそれが舞台で生きてくるのも皆さんの謙虚さと熱心さの証明です。ぼくも明日の夜出発します。久しぶりに東京で会える楽しみな人たちもいます。みなさん、体調に気をつけて、練習の成果をそのまま東京の舞台で発揮してください。
(ブログ 詩の散歩道 演劇だより 20191029 すはま)