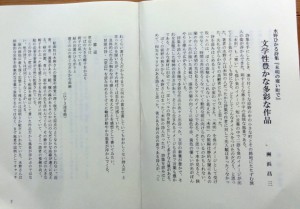2010年11月、香川県善通寺の水野ひかるさんが詩集『未明の寒い町で』(土曜美術出版)を出された。贈呈を受け率直な感想を書いて礼状をお送りした。後日「詩誌そばえ」へ書評を頼まれました。「そばえ」(「戯」)は徳島県板野郡板野町の扶川 茂さんが発行されている詩誌。2012年1月にⅢ4号が発行され書評が載りました。長い文章ですが紹介します。
水野ひかる詩集 『未明の寒い町で』
文学性豊かな多彩な作品
洲 浜 昌 三
詩集を手にしたとき、凍り付くような原野の中の小さな町とその路地にたたずむ旅人の姿が浮かんできた。刺すような寒さの中の孤独な風景である。
「未明」も「寒い」も強い負のイメージ。短い言葉の中で二語も負のイメージが出てくると負のイメージも倍になる。(略)
詩を読みはじめるとイメージが変わってきた。「未明」を負のイメージとして受け取ったのは、ぼくの誤解かもしれないと考えた。「未明」の視線は静的な闇にあるのではなく、時間と共に明るくなっていく動的な朝に向けられているのかもしれない、と思った。闇の向こうに希望の光が見えるプラスのイメージである。そう思って本を見ると、狭山トオル氏が描いた表紙は、漆黒の闇の向こうに緑色や赤、黄色の優しいが光がぼんやりと滲んで広がろうとしている。
詩集を読んでいくと多様で多彩な作品に次々と出会った。文学の素養が豊かで、それを基盤にした精神の自由さがあり、そこから生まれるイメージも自由で言葉も豊かである。どんな素材に出会っても一定レベルの詩を創りだしていく多才な力量がある。
ぼくの視野の狭さから、水野さんはまったく未知の詩人だったが、詩集を読みはじめて、相当キャリアのある詩人だと思った。ある詩の会の席である詩人が、「これくらい書ける人だから今までに何かの賞を受賞していてもおかしくない詩人だ」と言ったのを聞いたが、その時ぼくは思わず同感していた。
具体的に作品に触れながら感じたり考えたことを感想として書いてみたい。
冒頭の詩・『窓辺』を読み始めるとすぐに輪郭が鮮やかな風景が浮かんでくる。
窓 辺
窓辺の女は
つばの大きな帽子をかぶり
椅子に座っている
緑の田園のひろがりと
遠くの山の青くなだらかな曲線
(以下3連省略)
絵画性は水野さんの資質や感覚に深く根ざした原点のようなものにちがいない。近景、中景、遠景があり、縦、横の線がありその中に山のなだらかな曲線が遠くに見える。緑の田園、青い山、窓や椅子の色も浮かんでくる。その静の中に、つばの大きな帽子をかぶった動を感じさせる女性が椅子に座っていて、そこへ読者の視線が向く。絵に必要な要素が自然に配置されている。
脳の細胞に最も強く記憶として残るのは図柄とか絵だといわれている。水野さんの詩の特徴の一つがここにあるのではないかと思う。抽象的な世界を抽象的な言葉で表現するのではなく、まず風景や図柄としてキャッチし、その風景を重ねて抽象的な世界を伝えようとする。
人 生
山ひとつ抜けると
雨が降っていた
振りかえると
トンネルの奥の
通り過ぎたレールのあちら側では
まだ陽が照っている
傘を持っていることを確かめ
すこし安心する顔
傘を持たずにきたことを
少し後悔する顔
(略)
この詩も鮮やかに風景が目に浮かぶ。遠近、動静、明暗、ズームアップ、ズームアウト。言葉も端的でどこか俳句のような発想や配列、リズムがある。言葉のリズムという点では散文詩を含めどの詩にもリズムがある。それは水野さんの呼吸なのだろう。生理的な呼吸でもあるが美的意識を持って培ってきた呼吸でもあるだろう。
表現には俳句的な発想やリズムがあるが、表現しようとする世界は複雑で奥深く難解である。Ⅰのタイトルにもなっている『魂のかたち』などはその一つである。抽象的な魂に「かたち」という具体的な枠をはめて、あくまで具体に徹して魂を描こうとする詩の技法に感心すると共に、ぼくの心に深く食い込んでくるものがあった。
『魂のかたち』
がすこしずつ大きくなる
雨水が溜まり 虫が住み
蛇が這い込む
そこは いつも
からっぽで
いろんなものの居場所になる
(略)
詩集のタイトルとなった『未明の寒い町で』はⅢ「覚悟のあとさき」の中で出会った。4連から成る詩だが、最終連だけを取り出してみる。
『未明の寒い町で』
夜の扉が軋りながら閉まる
未明の寒い町で
シナプスに繋がる懐かしさと
取り残された寂しさを味わいながら
ぷちぷちと目覚め
朝の光の中で
老いていく自分に 出会う
現在の心境を詩にしたのだろう。親しかった人たちは次々と去っていく。一日が終わり夜の闇が牢獄の扉がきしむように下りてくる。暗くて寒い居場所。懐かしい故人が昔と同じ姿で夢や回想に出てくる。朝がくると自分の置かれた位置を更に自覚する。「ぷちぷちと目覚める」という独特の表現はどんな感覚を伝えたかったのか正確には分からないが、ぼくには陽のイメージが伝わってくる。
重要なのは「老いた自分」ではなくて「老いていく自分」だとぼくには思える。30歳でも「老いていく自分」を認識する。10代でも老いへ向かっての進行中だ。その進行形の中で水野さんは独特の鋭い表現で今の心境を詩に留めたのだろう。
冒頭で詩集のタイトルのことを書いたが、この詩に出会ってぼくなりに納得することができた。「未明の寒い」は水野さん特有の印象を強めるアーティフィッシャルで文学的な修辞表現であり、「町」は現在の居場所を示す同様に修辞的表現だったのだろう。
後半のⅢには共感する詩が多かった。それは過去から未来への時間の感覚が背後に流れていて、現在のぼくの認識と共通するものがあるからだろう。(ぼくはもっと未明の寒い町に住んでいる)さらに言葉に力みや構えがなく、すーっと心の中に入ってくる詩が多い。表現は平易に見えるが最後に大きなジャンプや飛翔があり、それに出会うとどこかへ吸い込まれて行くような高揚感に襲われる。詩を読む醍醐味とでもいうのだろう。
分かりやすいというのは作者の発想や表現が対象に対してストレートだからでもある。例えば『千の夜を』ではそれぞれの連の冒頭が動詞ではじまる。連の冒頭の2
行だけ取り出してみる。
歩いている
とぼとぼと 土埃の道
走っている
一心に 家に向かう道
(略)
結論や重要なことを先に伝え、補足や修飾的な表現はその後に付加するというのが英語の発想である。そのつもりで一連の詩を見ていくとそういう発想や表現にあちこちで出会う。水野さんの詩の明快さや躍動感はここにもルーツがありそうだ。京都女子大国文科卒とあるが、どこかで外国文学に没頭した時期があるのかも知れない。 (略)
最後に『ロッキングチェア』7連以降を引用して、詩自体に語ってもらい、ぼくの饒舌を終わることにする。
『ロッキングチェア』(冒頭より5連は省略)
少し仮寝している間に
おじいちゃんが亡くなり
新しい家に引っ越し
子供たちは 大人になり
おばあちゃんも 逝った
居間に置かれた
きしきしと鳴る ロッキングチェア
座ると揺れる時が流れ
新しい家族が増え
まっさらな魂のような赤ん坊が
ひとり ふたり さんにん よにん
うまれた
わたしは いつのまにか
おじいちゃんおばあちゃんと呼ばれ
過ぎ去った夢を見ていた
大きなロッキングチェアに
双子の孫が
並んで座っている
ふたたび繰り返す時のはじまりのように
揺れている