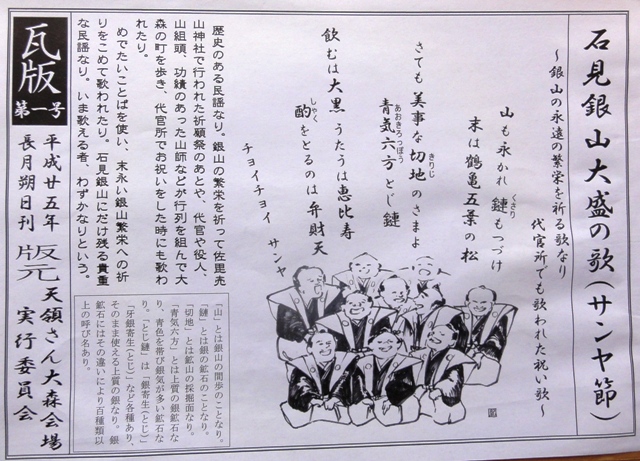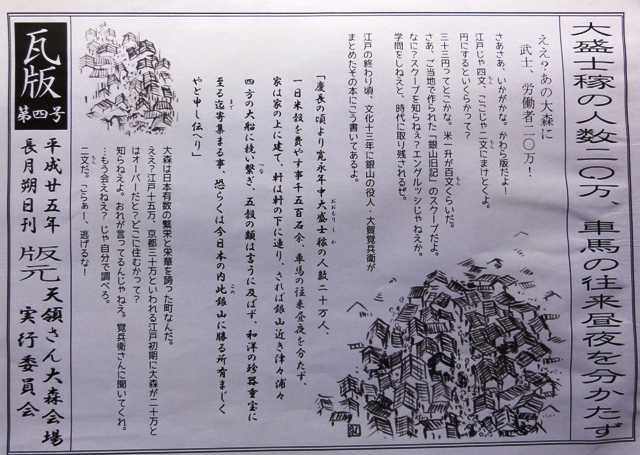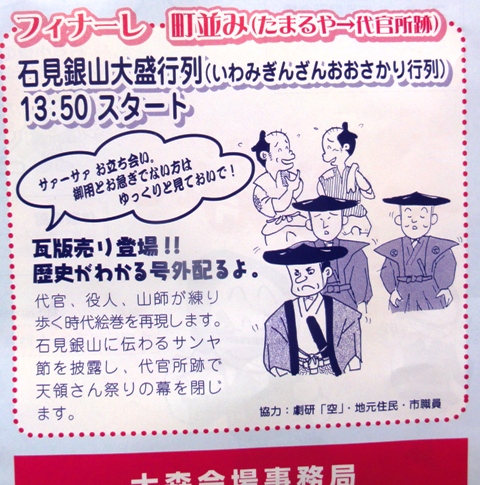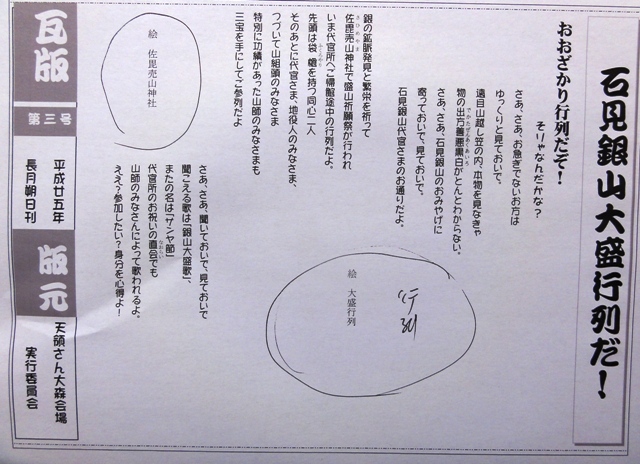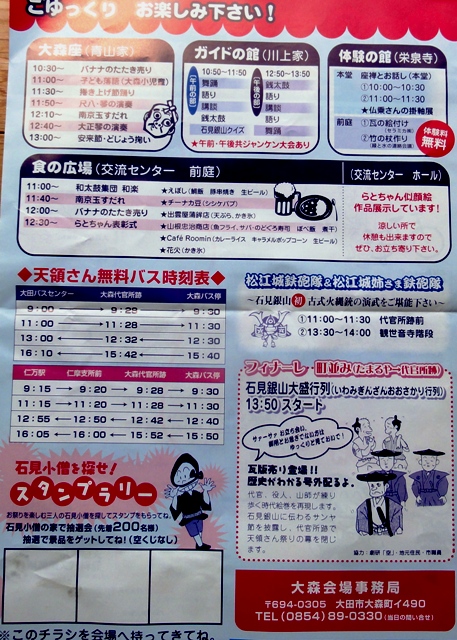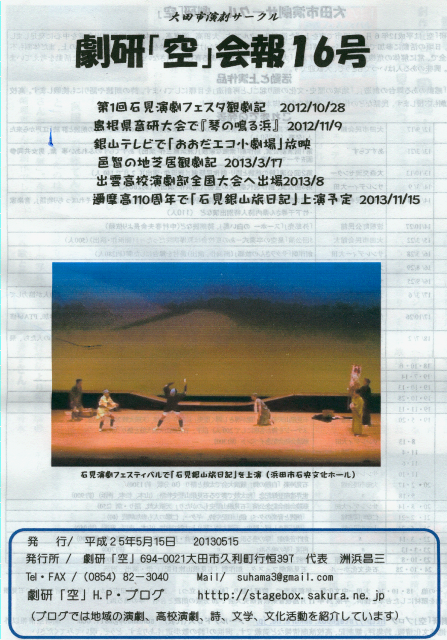一部の人にはメールで、また他の人には印刷物を郵送、持参してお知らせしましたが、つぎのように大幅に日にちも場所も変更します。
「石見銀座案旅日記」の練習日変更について連絡 H25、10,11
おつかれさまです。練習日の変更についてお知らせします。10名のメンバーには12日の24時過ぎにメールでお知らせしました。 10月始めから毎週、月曜日、金曜日に川合町つくりセンターで練習していますが、 町つくりセンターの都合やキャストの仕事、各種行事などで計画通りに行きません。 予定していました14(月)、21(月)、25(金)は取りやめつぎのように変更します。もちろんこの日でも仕事や出張など都合がつかない人もありますが、代役で読み合わせや立ちげいこしたいと思います。
15日(火)19時~21時 市民会館隣の町作りセンター会議室。
18日(金)19時~21時 川合町つくりセンター
20日(日)13時~17時 市民会館隣の町作りセンター研修室(民謡の部分も練習)
27日(日)17時~21時 上記に同じ (洲浜は高校演劇県大会講師で松江)
27日以降は各自の予定など聞きながら決定しますが、基本的には月曜日、金曜日、川合町つくりセンターで行います。(月は都合が悪い人がいますので変更する可能性あり)
さらにいい台本にするために常に検討し議論しながら進めていますが、9月末に郵送しました脚本を修正し、印刷し直し前回の練習時(10月11日)に渡しました。その後、後半部分で若干の修正をしましたので、25~28ページをさらにコピー(B4版)しました。
まだの人には郵送したり練習日に渡しますが、セリフ自体はあまり変えていません。 仕事や家事の都合などいろいろで、全員集まって練習というわけにはいきません。各自、自分のパートのセリフを何度も繰り返して身体に覚えさせてください。
何度も読んで単なる暗記をする野ではなく、場面や相手の表情、心の動き、自分の気持ち、お客さんの反応などなどをイメージしながらで覚えることが大切です。そのほうが表現が生き、記憶にもしっかり定着し本番でも臨機応変な対応ができます。
別の話でーす。11日に文化プロデユースス・テップアップ講座で決定した2/2のイベントについて文化協会、市の担当者、吾郷議員、劇研空3人で会合を持ちました。結局、劇研空が計画していたイベントをやる事に決まったために、空がイベントの内容もプロデ-スもやるような感じになってしまいました。(当初から、こうなるだろうという予感があったので、何度もその問題点を提起しましたが・・・。さて、どうするか)
発表会場は市民会館中ホールが予約してありますが、客席は約150。サンレディは改修で使用不可。あすてらすは2月2日はOKですが、前日は17時まで予約が入っています。一年前からの計画ではないので、会場問題や出し物など難題が山積しています。
企画会議か、プロデユーサーが企画して、「40分で三瓶の民話を劇にして上演してくれませんか」と劇研空へ持ち込むのが普通のかたちです。なんんでこうならないのだろう。邇摩高校での上演もありますしゆっくりしてはおれません。